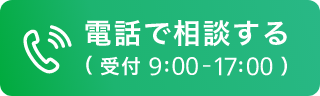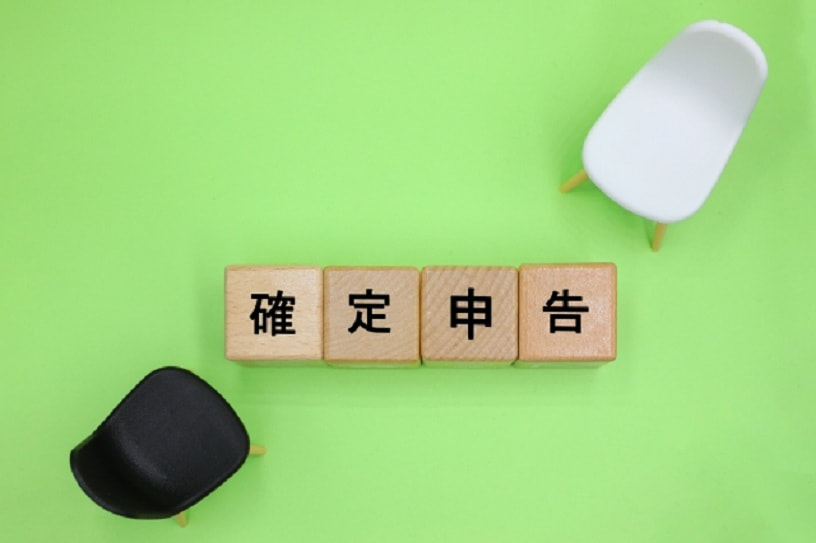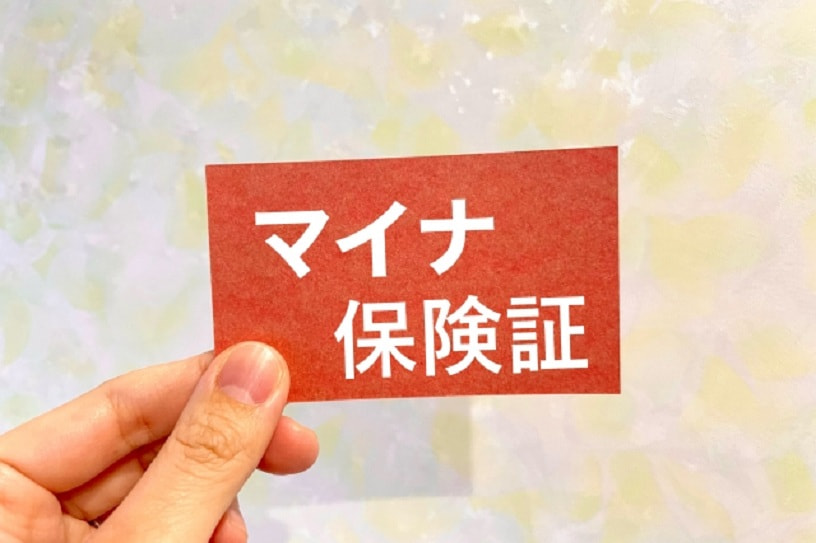読み物
相続吉田修平法律事務所 弁護士 吉田 修平「相続に関する登記制度の改正について」

1.相続登記の義務化と相続人申告登記
不動産登記簿、住民票、戸籍等を調べても、所有者が誰かを特定することができない土地(特定不能)と、所有者が誰かを特定することができても、その所在を知ることができない土地(所在不明)を「所有者不明土地」と言いますが、その発生の予防や利用の円滑化のため、令和3年4月に、民法など20余りの法律が改正されました。
その一環として不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されるとともに、相続人申告登記という新しい制度も創設されました。
従来、わが国では不動産について相続が発生しても、必ず相続人が相続登記をするわけではありませんでした。遺産分割についても期間の制限はなかったため、何代にもわたって、不動産について相続登記をしないで放置するという事態が多く発生し、それにより所有者不明の土地などが多く発生していたのです。
そこで、相続登記をすることを義務化し、相続により不動産を取得した相続人は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくその申請を怠ったときは10万円以下の過料に処せられることとなりました(不動産登記法76条の2、164条1項)。
他方、登記を申請する相続人の負担を軽減するため、相続人からの簡易な申し出による氏名、住所のみの報告的な登記(相続人申告登記)制度を新設し、相続が開始したこと及び申請人が法定相続人であることを登記官に申し出ることができることとされ、前記の期間内にこの申し出をすれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされることとなりました。ただし、この申し出をした人は、その後、遺産分割によって所有権を取得したときは、その分割の日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の3)。
なお、相続人申告登記は、報告的な登記であり権利の登記ではないため対抗要件にはなりません。
また、相続登記を申請する場合と比べて、法務局に提出する書類も大きく軽減されています。相続登記を申請するには、原則として被相続人が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍を提出する必要があるのですが、相続人申告登記の場合は、権利の登記ではないため、持分割合を証する情報を提供する必要はなく、被相続人が死亡したことと、申し出をしている人が相続人であることを証すれば足ります(例えば戸籍の抄本でも足ります。)。
今回の不動産登記法の改正は令和6(2024)年4月1日から施行されたのですが、ここで注意しなければならないのは、施行日より前に起きた相続についても相続登記は義務化されたということです。
極端に言えば100年以上も前の明治時代の所有者の氏名が載っている登記について、3代も4代も後の相続人が、原則として施行日から3年以内である2027年3月31日までに相続登記を行わなければ過料の制裁を受けるということになりました(なお、改正法の施行日前に相続が発生したが、そのことを知ったのが施行日の後であったという稀なケースの場合は、やはり知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。)。
2. その他の登記制度の改正
従来は、遺言により「相続分の指定」を受けた人や、遺言により「遺産分割方法の指定」がなされ(いわゆる「相続させる旨の遺言」です。)、それに従って特定の不動産を相続することになった人は、遺贈を受けた人とは異なり、相続登記がなくとも、法定相続分を超える部分について第三者に権利を対抗できることとされていました(最判平成5年7月19日等(相続分の指定)、最判平成14年6月10日等(遺産分割方法の指定))。
遺贈が特定承継であるため、遺贈を受けた人と共同相続人の1人から法定相続分(共有持分)の譲渡を受けた第三者との関係は民法177条の対抗問題になります。これに対し、相続分の指定及び遺産分割方法の指定は、いずれも相続を原因とする「包括承継」なので、他の共同相続人から法定相続分を取得した第三者は民法177条の第三者には当たらないことが理由とされていました。
しかし、平成30年の相続法の改正(令和元年7月1日施行)により、遺贈、遺産分割、相続分の指定、及び遺産分割方法の指定のいずれの場合であっても、相続により遺産である不動産を取得した相続人は、その旨の登記をしなければ、他の共同相続人から法定相続分の譲渡を受けた第三者に、自己の法定相続分を超える部分については、対抗できないこととされたのです(民法899条の2)。
従って、従来であれば遺言により「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定」を受けた相続人は、登記をしないでいても、他の共同相続人が法定相続分を第三者に譲渡した場合でも、その第三者に対抗することができたので、何もしないでいても良かったのです。しかし、相続法の改正後は、そのような場合でも早く相続登記をしておかないと安心できないことになったので、注意を要します。