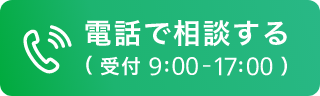読み物
相続吉田修平法律事務所 弁護士 吉田 修平「相続の承認と放棄」

相続とは、自然人の財産法上の地位又は権利義務をその者の死後に特定の者に承継させることである(民法第896条)。
相続財産は、被相続人の有する相続開始時(被相続人の死亡時)の財産であり、相続財産には、積極財産(権利)だけではなく消極財産(義務)も含む。
相続は、被相続人の死亡によって開始する(民法第882条)。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に、相続について、単純承認・限定承認又は放棄をしなくてはならない(民法第915条)。
承認も放棄も相続開始後に行われる。
相続の放棄及び限定承認は一定の方式を必要とするが(民法第924条、第938条)、単純承認は何らの方式も必要としない。
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継する旨の意思を表示することである(民法第920条)。
実務的には、法定単純承認(法律により単純承認したものとみなされる場合。民法第921条)となる場合が一般的である。具体的には、
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
② 3か月の考慮期間を経過した場合
③ 相続人が背信行為(相続財産の隠匿等)をした場合
である。
単純承認により相続財産は相続人の財産と完全に融合することになり、以後、独立性を失うことになる。
限定承認とは、相続財産がプラスかマイナスか不明な場合に、「相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を承継する」との意思を表示することである(民法922条)。
限定承認の場合には、3か月以内に、裁判所に相続財産の目録を提出し、限定承認をする旨を裁判所へ申述しなければならない。
相続が開始されると被相続人の権利及び義務の一切は相続人に帰属することになるが、相続放棄とは、このような相続の効果を相続開始時に遡って消滅させる意思を表示することである。
相続の放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項、同法第938条)。
相続を放棄した場合には、放棄をした者は始めから相続人でなかったものとみなされる(民法第939条)。
なお、相続欠格又は廃除の場合と異なり、相続を放棄した場合には、放棄した者の直系卑属は代襲相続することができない。
上記の3か月の期間(熟慮期間)の起算点は、
①相続人が相続開始の原因事実を知り、かつ、②それにより自己が相続人になったことを知った時である。
この点につき、熟慮期間の経過後に消極財産(借金等)の存在を知った場合に問題が生ずるため、最高裁は被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の諸状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続人においてこのように信じるにつき相当な理由がある場合には、例外的に、③相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するとしている(最判昭59・4・27民集38巻6号698頁)。
また、3か月の熟慮期間内に、相続財産の調査が完了しない場合もあるため、利害関係人(相続人も含まれる)又は検察官の請求によって被相続人の住所地又は相続開始地を管轄する家庭裁判所の審判によりこの期間を伸長することができる(民法915条1項但書)。