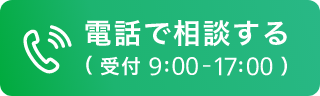読み物
社会貢献日本経済新聞編集委員 辻本 浩子コロナ時代を乗り切る「目薬」術

新型コロナウイルスの感染拡大が続いている。医療体制の整備など、ウイルスそのものへの対応はもちろん必要だ。それと同時に、コロナによって経済的、社会的な苦境に陥った人をどう支えるかが、2020年の大きな宿題だ。
自助、共助、公助――。いずれも人を支える力となる。最初にくるのは「自助」だ。しかしいまのような激変時には、自助だけでは限界があろう。とりわけひとり親家庭や非正規で働く人など、もともとの経済基盤が弱い人には、しわ寄せが一気に集まる。
必要なのは、「公助」と「共助」だ。いずれも欠かせないものだが、とりわけ共助には共助ならではの強みがあるだろう。
公助は政府や自治体による支援だ。予算規模は大きいが、すべてをカバーできるわけでもない。分野ごとに縦割りが強いため、それが原因で十分な支援が届かないこともある。
一方、社会の助け合いである共助は、より柔軟だ。子育て家庭への支援、若者の就労支援......。ときに行政と連携、補完し合いながら、さまざまな活動が行われている。なにより、より身近なところから寄り添った支援を届けることができるのが特徴だ。
「目薬」という言葉がある。作家で精神科医の帚木蓬生さんが複数の著書で書いており、自分も読んで感銘を受けた。すぐに解決できないことでも、見守ってくれる目があれば、それ自体が助けになるという発想だ。
「ヒトはだれも見ていないところでは苦しみに耐えられません。ちゃんと見守っている眼があると、耐えられるものです」(「ネガティブケイパビリティ」朝日新聞出版より)。精神科医として長く患者を支えるなかで、この「目薬」を大切にしているという。
「目薬」の効用は、ほかの多くの場面でも同じだろう。自分は一人ではない、気にかけてくれている人がいる。これは大事なよりどころになる。そして共助は、この目薬の力をとりわけ発揮しやすいのではないか。
もちろん、行政による公助でも、寄り添い型の支援をもっと増やしたい。コロナ禍のなか、社会にはもっと目薬が必要だ。わたしたちにもできることはあるだろう。例えば地域で、誰かに声をかけてみる。それが、誰かにとっての目薬になっていくかもしれない。
日本財団が提唱する、遺贈という名の選択
「気にかけてくれる人がいる」ことで救われた経験がある人は、困っている人を「見守る目」を持つようになります。日本財団がめざすのは、そのような「みんなが、みんなを支える社会」です。
日本財団遺贈寄付サポートセンターでは、遺言書で自分の財産を社会貢献のために使いたいという方のご相談をお受けしています。「未来の子どもたちを見守りたい」とお考えの方からのご相談も多くございます。お気軽にご連絡ください。