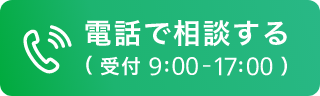読み物
終活日本経済新聞編集委員 辻本 浩子「稲むらの火」が見た未来

地震の多い日本で、防災の先駆例とされるのが「稲むらの火」のお話だ。教科書に載っていた時期もあり、聞いたことがある人もいるだろう。
大きな地震が起き、沖合から津波が陸に迫ってきた。高台にいた男性にはそれが見えているが、下にいる村人たちは気付かない。男性は自らの収穫した稲むらに火をつけることで早期に警報を発し、避難させることで村人の命を救った、という話だ。
この話は、実話をもとにしている。1854年11月5日(旧暦)、安政南海地震のさいの和歌山県でのできごとだ。ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)がこのエピソードを英語で作品にまとめ、世界でも知られるようになった。国連は11月5日を「世界津波の日」に定めている。このときの話が、もとになっている。
とっさに村人のために、稲むらに火をつける。この男性の発想力、決断力はすばらしい。さらに「稲むらの火」には、後日談がある。またいつくるかもしれぬ津波に備えて、村に大堤防をつくる工事に乗り出すのだ。そのための費用に、彼は私財を投じた。「住民百世の安堵を図る」。この男性、濱口梧陵の言葉はいまも伝わっている。
公共への寄付や社会事業の、いわば先駆けかのひとつもしれない。単にお金がある、余裕がある、からできたことではないだろう。よりよい明日のために、自分は何ができるのか。その思いをかたちにしたのが、堤防工事だった。
堤防は、いまも大事に守られ、使われている。一方、この堤防だけでは被害を完全に防げないことも分かっている。早期避難(稲むらの火)と、防災工事(堤防)。ソフトとハードの両面が欠かせない。いまでも年1回、地元の子どもたちが堤防に盛り土をし、防災への思いを再確認する。子どもたちも大切な担い手だ。
未来のために、何ができるか。だれかが一歩踏みだせば、その思いは広がり、次へとつながっていく。確実に社会を変えていく。それぞれの立場で、自分のできる範囲で。未来への夢を、自分のなかにともすことができる。それはだれにとっても幸せなことではないだろうか。
日本財団が提唱する、遺贈という名の選択
日本財団遺贈寄付サポートセンターでは、遺産を社会に役立てたいとお考えの方に、遺言書の書き方のご相談も承っております。「遺言書は書いておいた方が良いけれど、難しいそうだから」となかなか手が付けられない、また、いざ取り掛かろうとしたときに「何から始めれば良いかわからない」という方、どうぞお気軽にご相談ください。相談員が、ご不明ご不安な事項をお伺いし、丁寧に対応させていただきます。